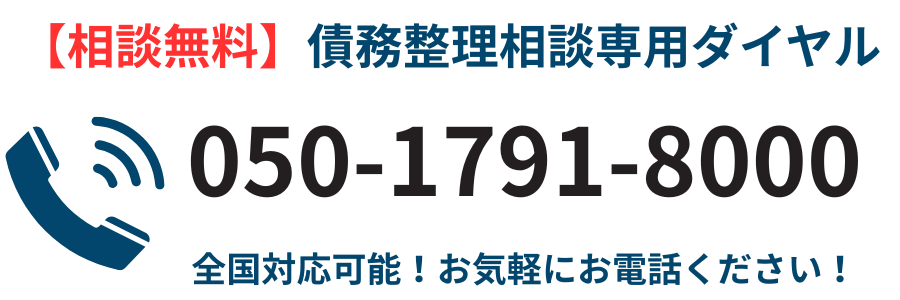「うちは財産も少ないし、相続で揉めるなんて関係ない」
「遺言書さえあれば、家族が争うことはないでしょう?」
実はその思い込みが、相続トラブルや余計な税負担を招くこともあります。
この記事では、相続でよくある5つの誤解を具体例とともに解説します。正しい知識を身につけ、後悔のない相続準備を始めましょう。
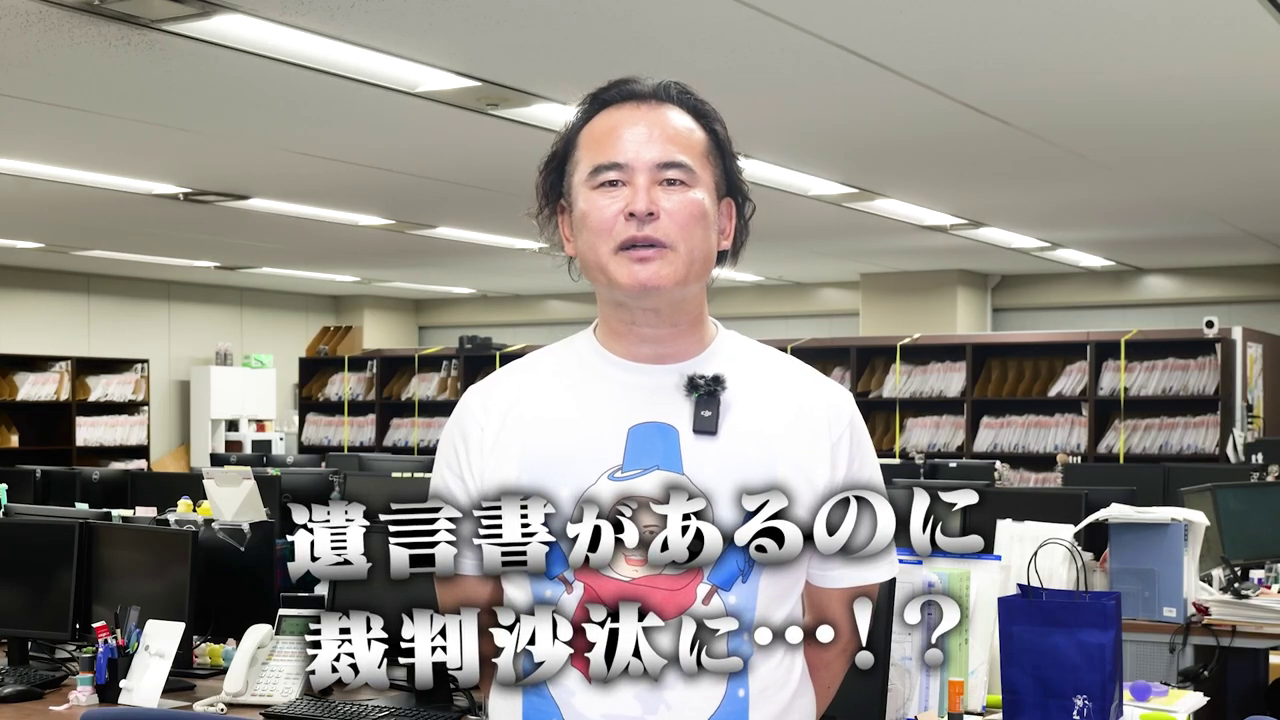
本題の前に:『相続放棄』の基本を知っておこう
解説に入る前に、重要なキーワードである「相続放棄」について簡単にご説明します。
相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産を一切受け継がないと意思表示する手続き
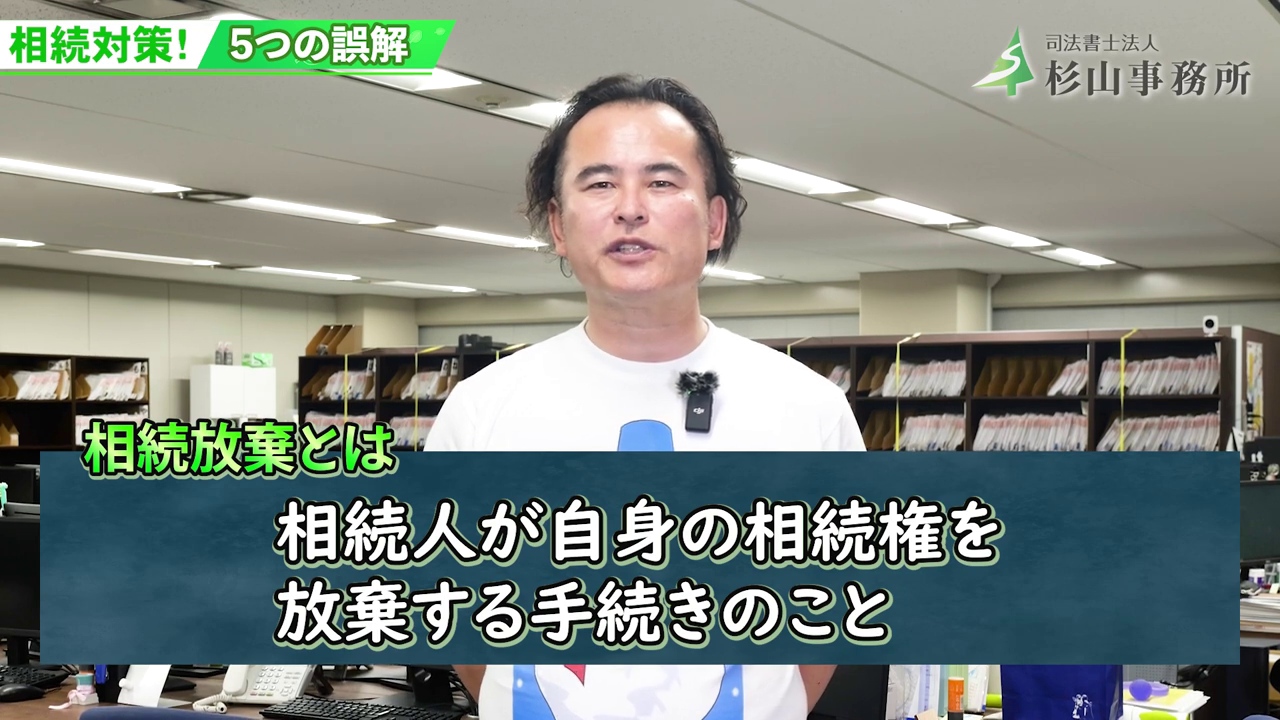
どんな時にするの?
- 故人の借金が財産を上回る場合
- 遺産分割のトラブルに関わりたくない場合
手続き方法は?
- 相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
一度相続放棄をすると、後から撤回することはできません。預貯金など、遺産の一部でも受け取ってしまうと、原則として相続放棄は認められなくなります。
相続放棄は、すべての財産を放棄することが前提となる重要な手続きです。
【必見!】相続対策でよくある5つの誤解
それでは、多くの方が勘違いしやすい5つのポイントを、実際の事例とともに見ていきましょう。
書類
誤解① 遺言書があればすべて解決する
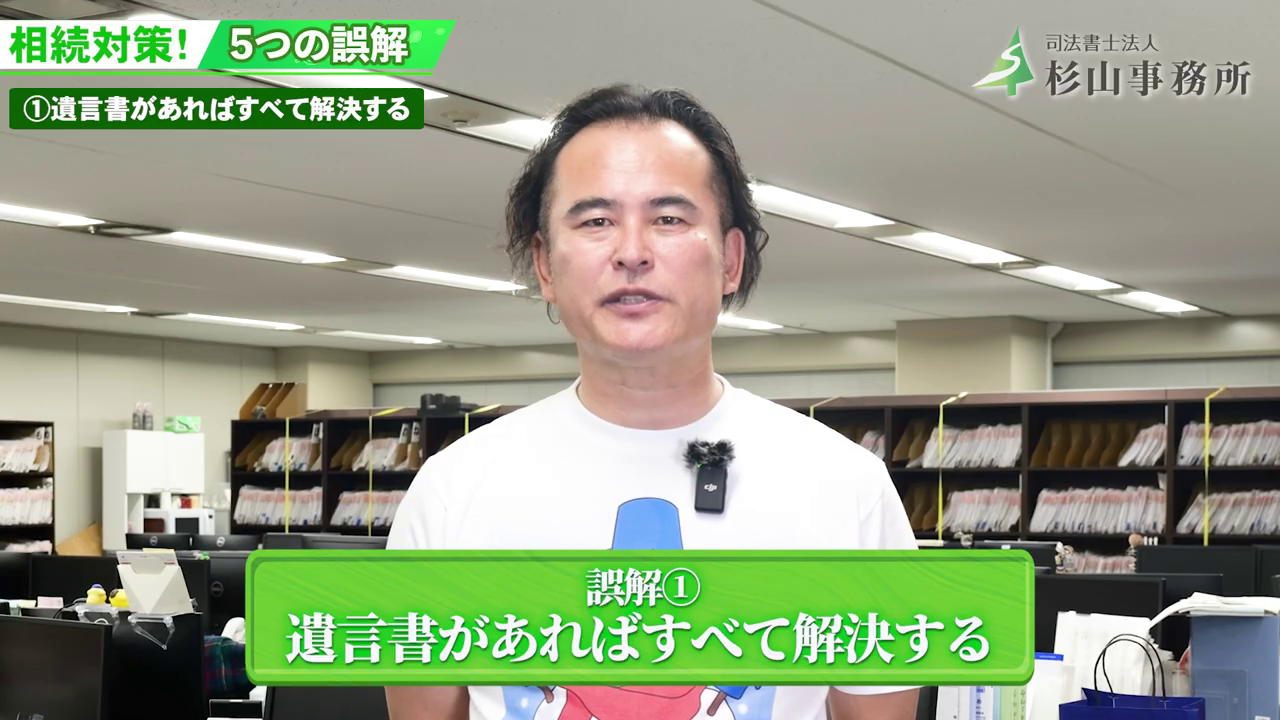
「遺言書があれば安心」と思われがちですが、内容によってはトラブルの火種になることもあります。
【実際の事例】
ある父親が「長男に自宅、次男に現金500万円」という内容の公正証書遺言を残して亡くなりました。
一見問題なさそうですが、次男が「自宅の価値は3000万円以上あるのに、現金500万円だけでは不公平だ!」と不満を爆発させ、結果的に裁判沙汰になってしまいました。
遺言書は故人の意思を伝える大切なものですが、相続人全員の感情までコントロールできるわけではありません。
遺言書を作成する際は、一方的に内容を決めるのではなく、事前に家族全員で話し合い、全員が納得できる形を目指すことが重要です。弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら内容を練ることをお勧めします。
誤解② 相続税の基礎控除内なら問題ない
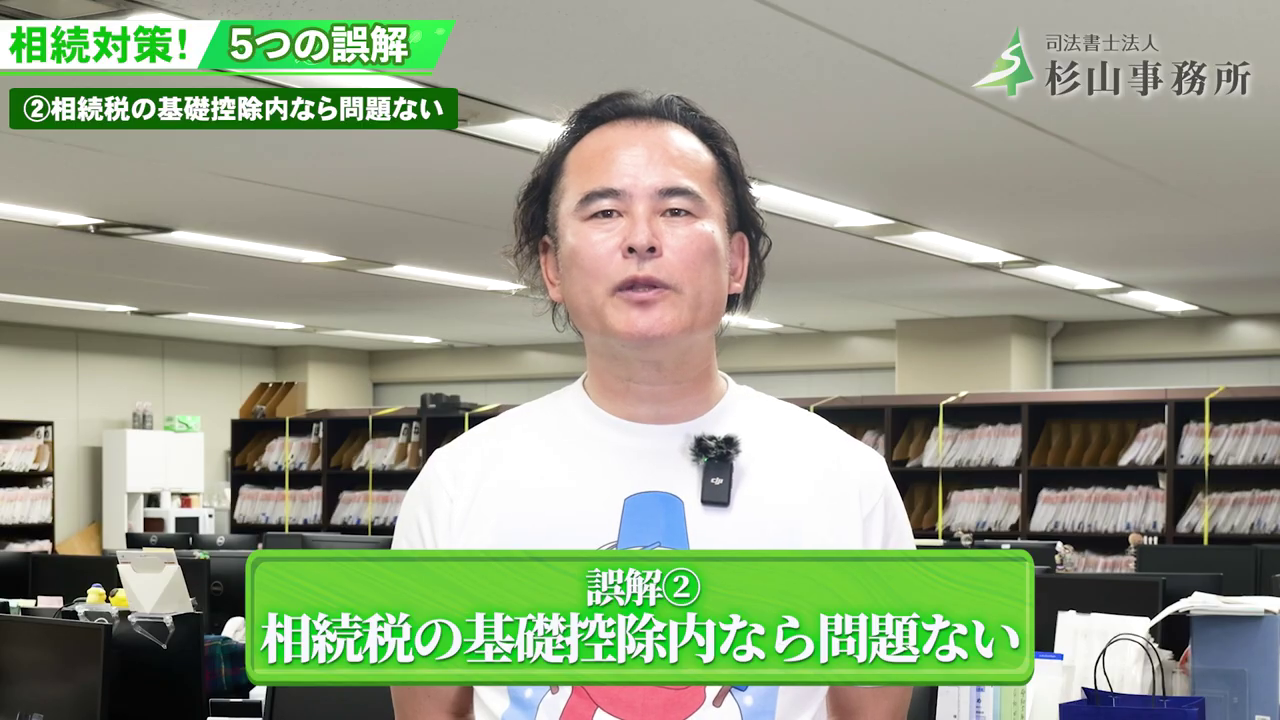
「うちは相続税がかからないから対策は不要」というのも危険な考え方です。
【実際の事例】
Aさんの父が亡くなり、遺産は現金2000万円、家屋3000万円、土地5000万円でした。相続人は母と子ども3人。相続税の基礎控除額は5400万円で、特例を使えば相続税はかからないケースでした。しかし、遺産のほとんどが不動産で現金が少なかったため、「どうやって公平に分けるか」で家族の意見が対立。不動産を売却するにも手間と時間がかかり、家族の間に亀裂が入ってしまいました。
相続の問題は、税金だけではありません。遺産の分け方(遺産分割)こそが、最もトラブルになりやすいポイントなのです。
相続税がかからない場合でも、不動産など分けにくい財産がある場合は、どのように分割するのか、あるいは現金化するのか、事前に計画を立てておくことが大切です
誤解③ 生前贈与をしておけば大丈夫
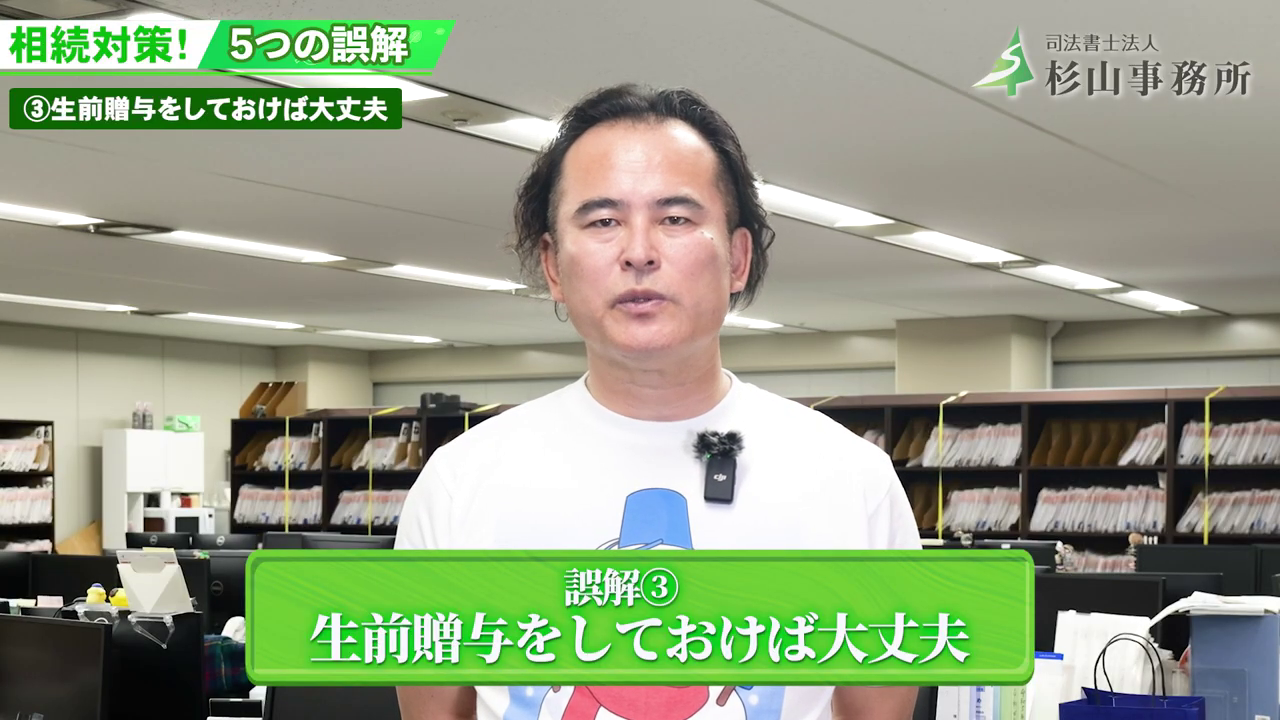
節税対策として有効な生前贈与ですが、やり方を間違えると逆効果になることがあります。
【実際の事例】
Aさんは3人の子どもに、贈与税のかからない範囲で毎年110万円ずつ贈与していました。しかし、亡くなる直前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されるルールを知らず、結果的に相続財産とみなされてしまいました。さらに、特定の子どもにだけ贈与していたことが他の兄弟に不公平感を与え、争いの原因となってしまいました。
生前贈与を行う際は、税金のルールを正しく理解することが不可欠です。また、相続人全員の公平性を保つことを意識しないと、かえって家族関係をこじらせる原因になります。
誤解④ 家族仲が良ければ争いは起きない
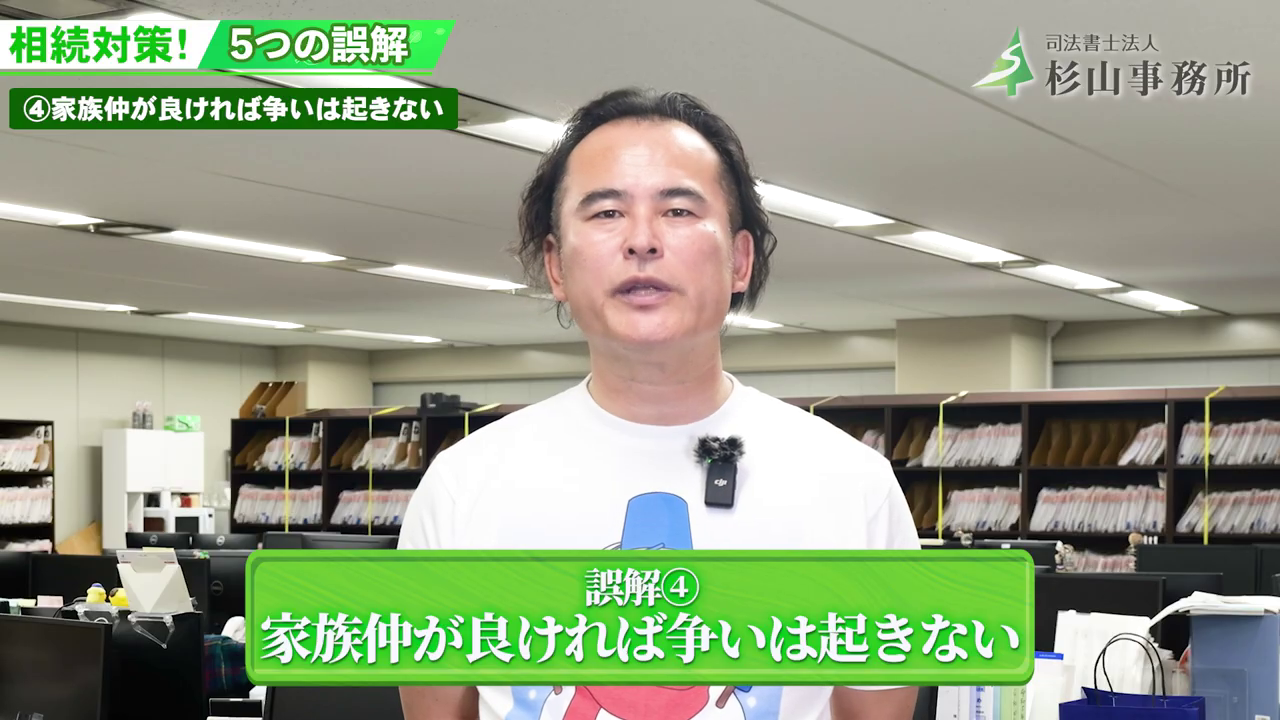
「うちは家族仲が良いから大丈夫」という言葉は、相続の現場で最もよく聞かれますが、残念ながら関係ありません。
【実際の事例】
普段から非常に仲の良かった兄妹。父が亡くなり、遺産は預金300万円と田舎の家1軒でした。妹は「家は使わないから売却して現金を分けたい」と主張しましたが、兄は「思い出が詰まった実家は手放したくない」と反対。分割方法をめぐって意見が真っ向から対立し、話し合いはまとまらず、良好だった兄妹関係が悪化してしまいました。
お金や不動産が絡むと、それまで顕在化しなかった価値観の違いが表面化し、感情的な対立に発展しやすくなります。
家族仲の良し悪しに関わらず、財産の分け方については客観的な視点が必要です。感情的にならず、専門家の力を借りて公平な分割方法を検討することが、円満な解決への近道です。
誤解⑤ 相続手続きは時間がたっぷりある
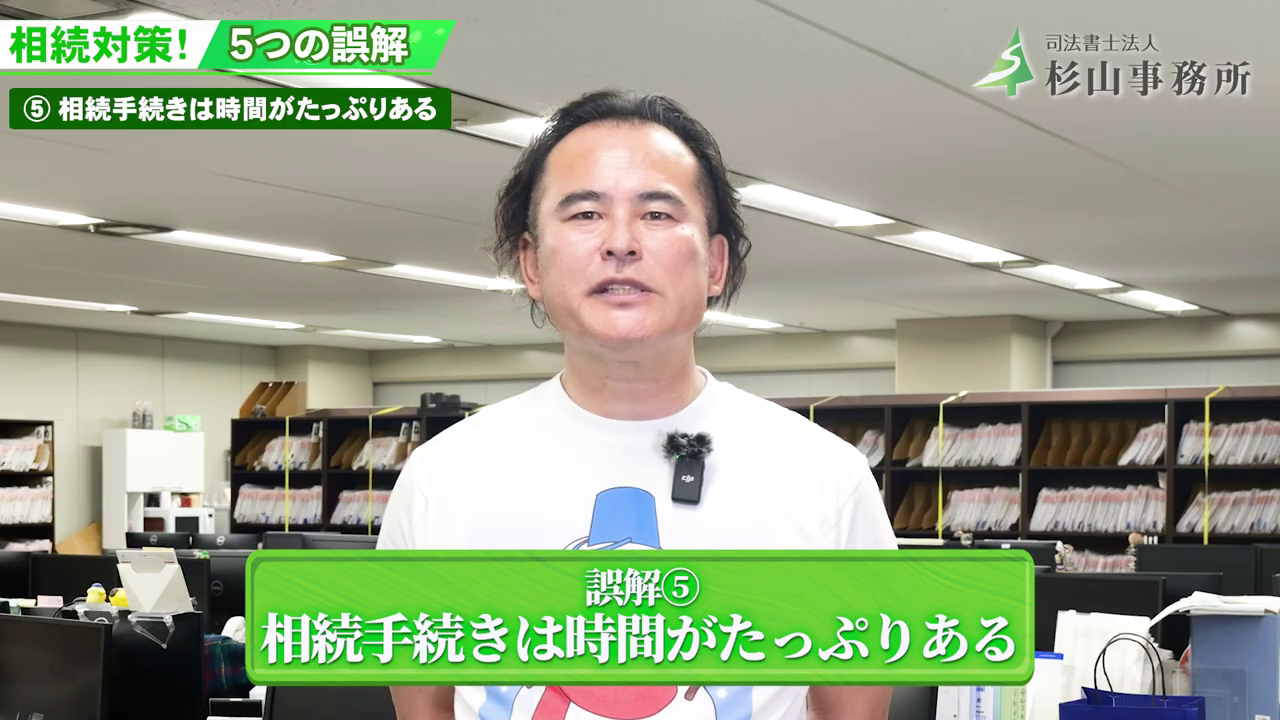
相続は、悲しみに暮れる間もなく手続きに追われます。時間に余裕があると思っていると、大変なことになります。
【実際の事例】
Aさんは父が亡くなった後、悲しみから相続手続きを後回しにしていました。その間に不動産の価値が変動したり、他の相続人との話し合いが遅れたりした結果、相続税の申告期限である「10ヶ月」を過ぎてしまいました。その結果、ペナルティとして加算税が発生し、余計な費用を支払うことになってしまいました。
相続に関する手続きには、それぞれ期限が設けられています。
相続手続きには期限があるものが多く、特に相続税の申告(10ヶ月以内)や相続放棄(3ヶ月以内)は重要です。何から手をつけていいか分からない場合は、速やかに専門家へ相談しましょう。
まとめ:正しい知識で後悔しない相続対策を
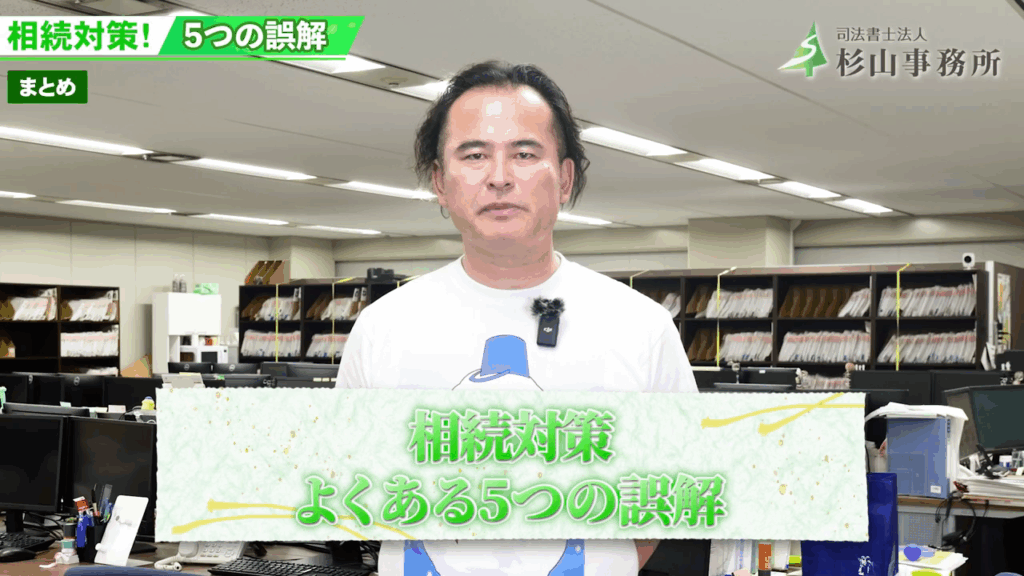
今回は、相続対策でよくある5つの誤解について解説しました。
① 遺言書だけではすべて解決しない
② 相続税がかからなくても問題が起こる可能性がある
③ 生前贈与を過信しない
④ 家族仲が良くても争いが起きることがある ⑤ 相続手続きには期限がある
相続対策は、問題を先送りにせず、早めに計画を立て、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが、家族間の無用なトラブルを防ぐ最大の鍵です。
この記事が、あなたの相続に関する不安を少しでも解消する一助となれば幸いです。もし相続に関するご質問やご不安な点がございましたら、いつでも杉山事務所にご相談ください。