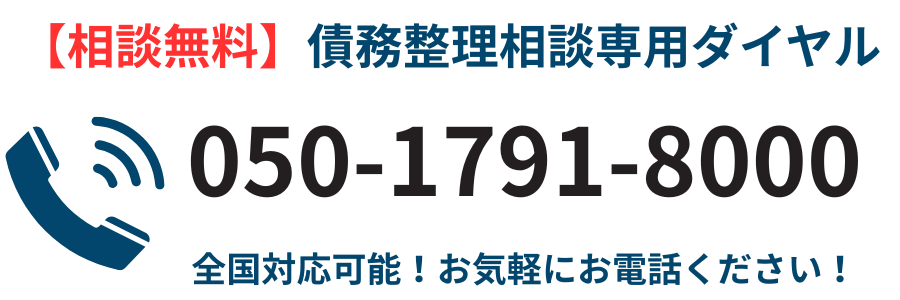「借金まみれの親の財産なんていらないから、相続放棄すればスッキリ解決でしょ?」
「相続人が誰もいなくなったら、残された家や土地はどうなるの?」
大切な方が亡くなられた後、多額の借金が発覚したり、誰も引き取り手のない不動産が残されたりした場合、「相続放棄」という言葉が頭をよぎるかもしれません。
確かに、相続放棄をすれば、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がなくて済む、というのが基本的な考え方です。しかし、「相続放棄をすれば、全ての問題から解放される」と思っているとしたら、それは大きな間違いかもしれません。
今回は、司法書士の杉山事務所の解説をもとに、「相続人がいない遺産の行方」と、相続放棄をしても残ってしまう「管理義務」という重要な責任について、プロの視点から分かりやすく紐解いていきます。
【結論】相続人がいない遺産は、最終的に「国のもの」になる
まず結論からお伝えします。
独身で身寄りのない方や、親族全員が相続放棄をした場合など、法律上の相続人が一人もいなくなった遺産(預貯金や不動産など)は、最終的に「国庫(こっこ)」に納められます。つまり、国の財産になるということです。
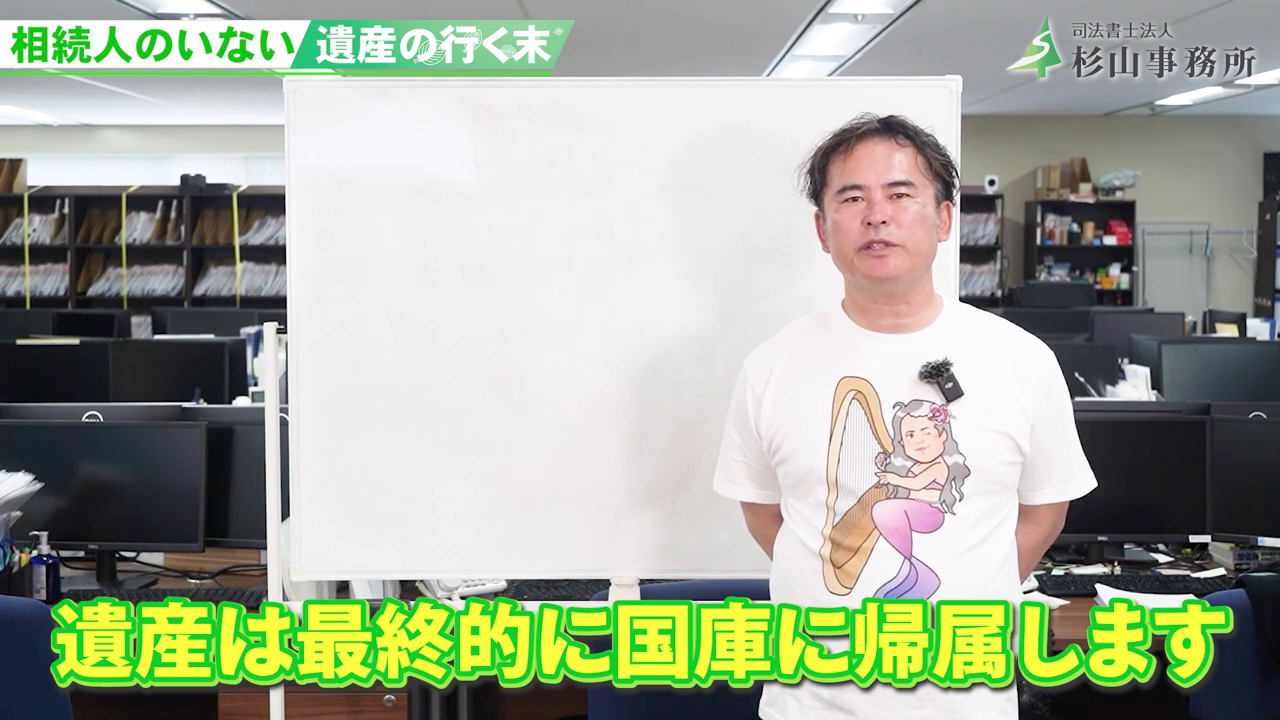
しかし、これは自動的に行われるわけではありません。
国のものになるまでには、非常に時間のかかる法的な手続きが必要であり、その過程で思わぬ費用や責任が発生することがあるのです。
相続放棄の最大の落とし穴「遺産の管理義務」
相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切引き継ぐことはできません。そのため、「これで一切関係なくなった」と安心してしまう方がほとんどです。
しかし、民法にはこう定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。(民法第940条)
少し難しいですが、要するに「あなたが相続放棄をしても、次の相続人や財産の管理者が現れるまでは、きちんとその遺産を管理しなさい」ということです。
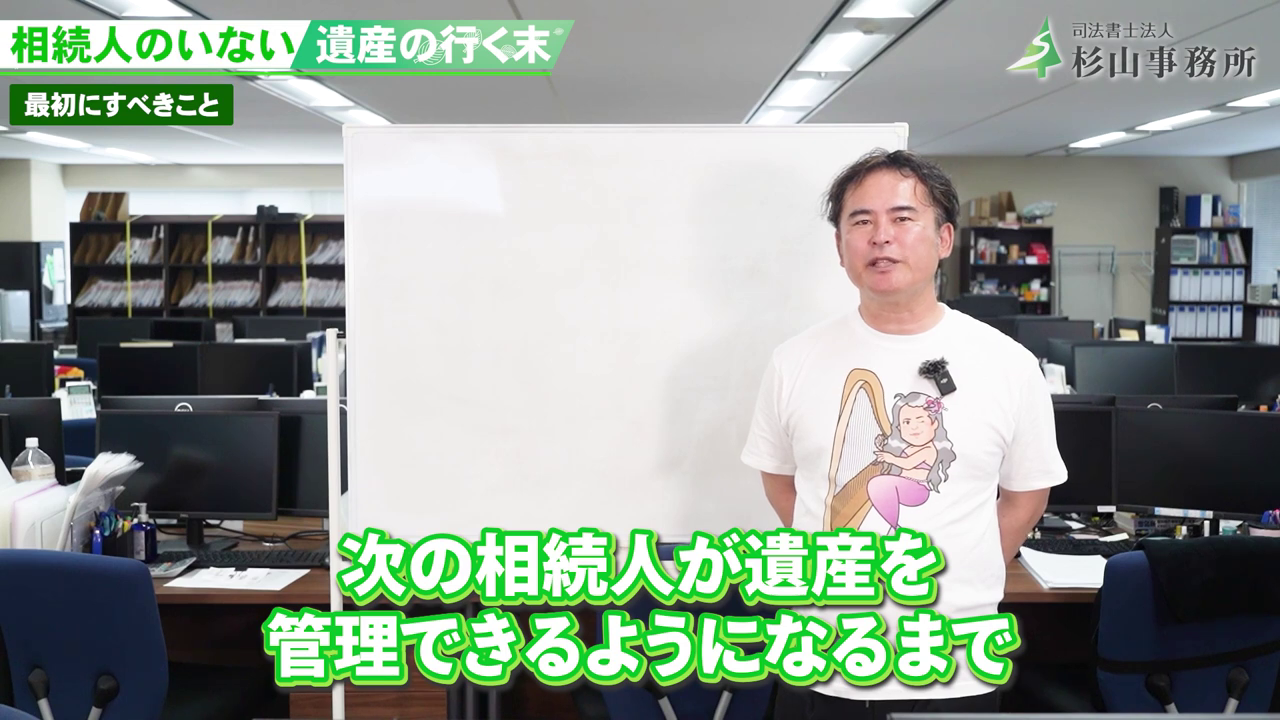
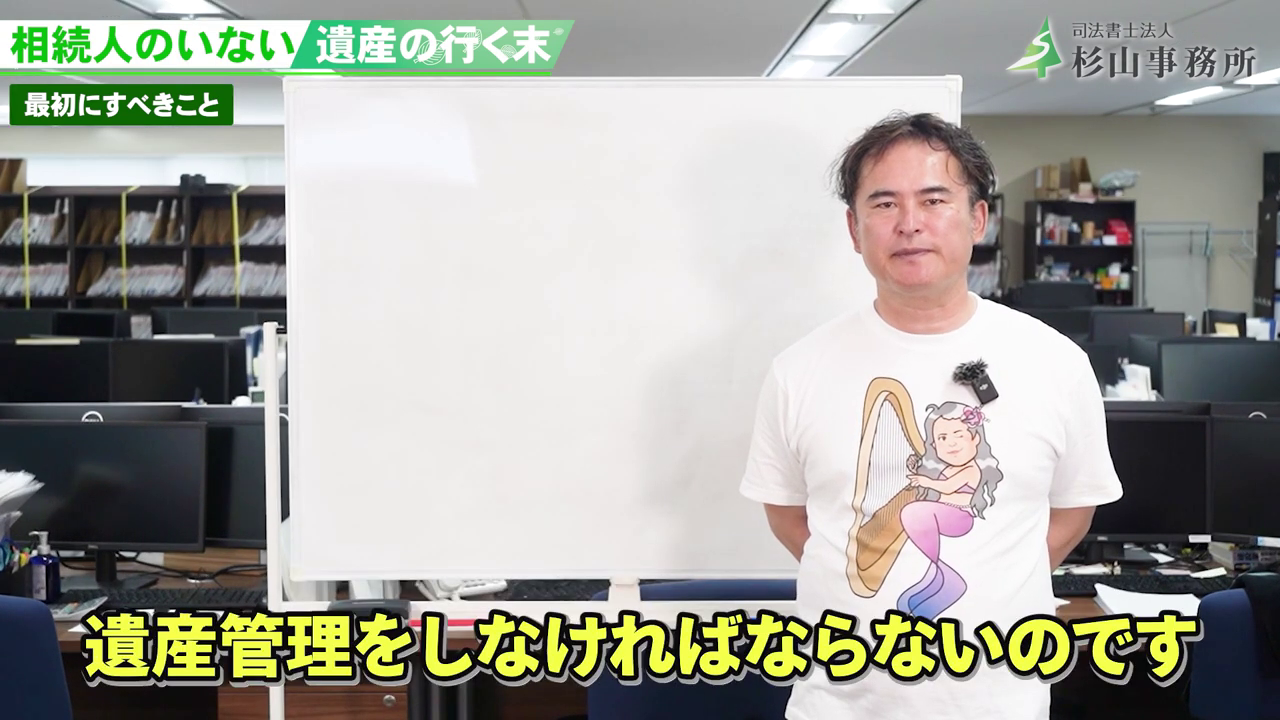
これが「遺産の管理義務」です。
なぜ「管理義務」が危険なのか
例えば、遺産の中に管理されていない古い空き家があったとします。あなたが相続放棄をした後、その空き家を放置した結果、
- 台風で屋根が飛んで、隣の家を傷つけた
- 老朽化でブロック塀が倒れ、通行人が怪我をした
このような事態が発生した場合、被害を受けた人から損害賠償を請求される可能性があります。相続放棄をしたにもかかわらず、「管理を怠った責任」を問われるかもしれないのです。
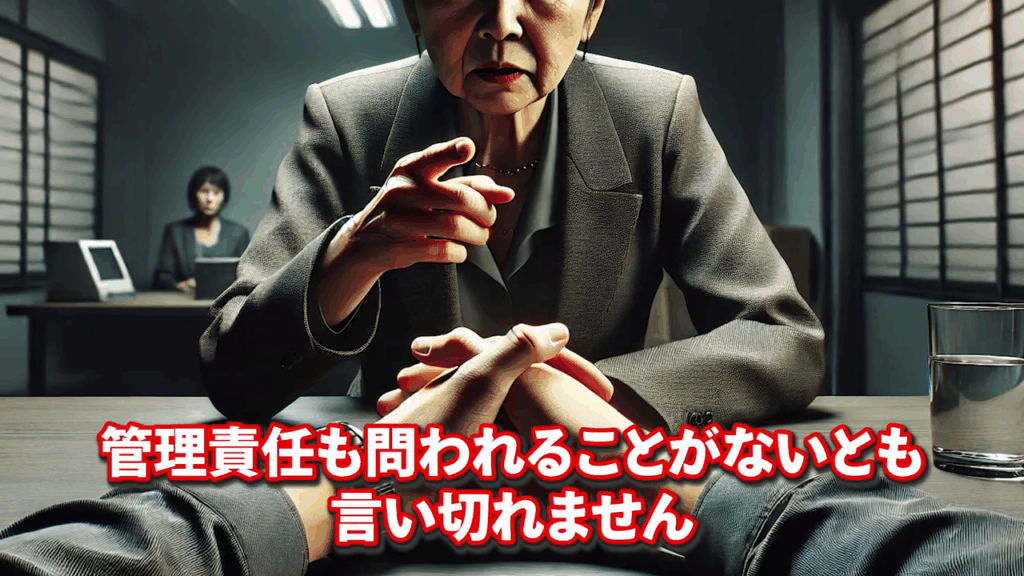
もちろん、遺産が預貯金だけの場合や、そもそも財産が何もない場合は、この管理義務が問題になることは稀です。しかし、管理が必要な不動産などが遺産に含まれる場合は、決して無視できないリスクなのです。
管理義務から解放される唯一の方法「相続財産管理人」
では、この厄介な管理義務から完全に解放されるには、どうすればよいのでしょうか。
その答えが「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」の選任です。
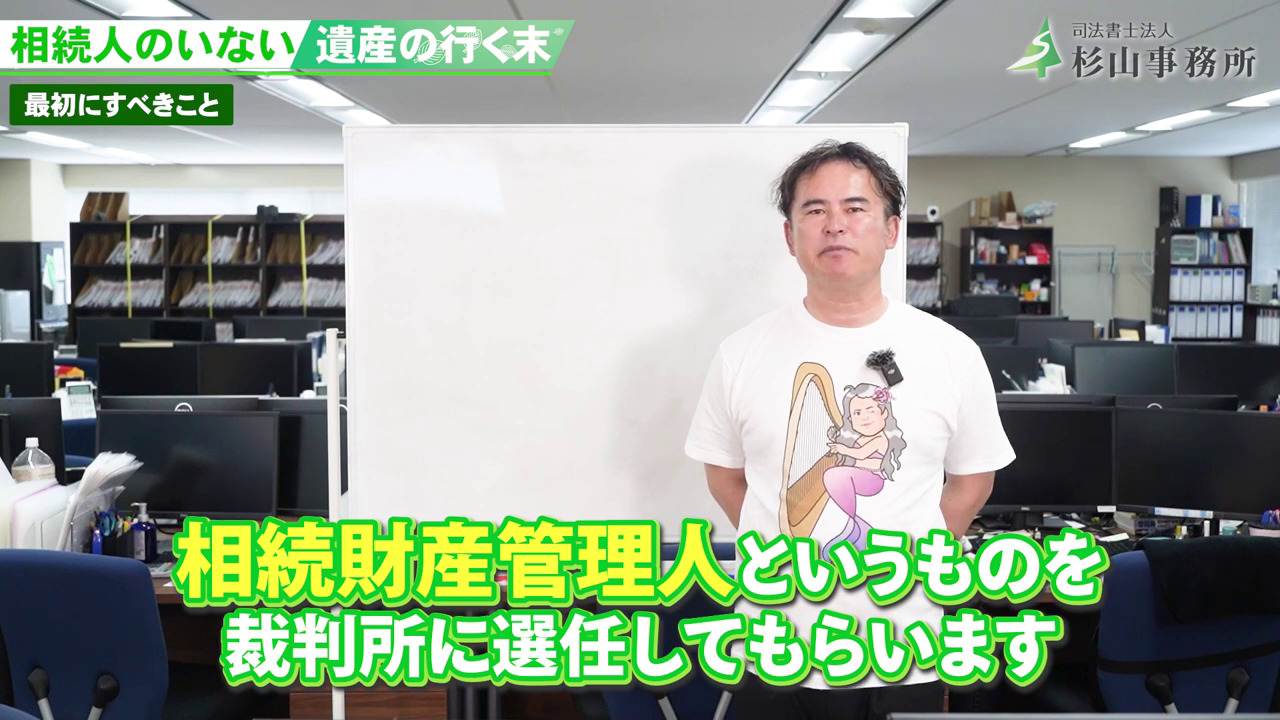
相続財産管理人とは、その名の通り、亡くなった方の財産を管理・清算するために、家庭裁判所によって選ばれる専門家(主に弁護士が選任されます)のことです。
この管理人を選任してもらうことで、ようやくあなたは遺産の管理義務から解放されます。
誰が、どうやって選任を申し立てる?
相続財産管理人の選任は、「利害関係人」が家庭裁判所に申し立てることで手続きが始まります。
利害関係人にあたるのは、主に次のような人たちです。
- 債権者: 故人にお金を貸していた人など。遺産からお金を回収したい場合に申し立てます。
- 相続人(相続放棄をした人): 前述の「管理義務」から逃れるために、自ら申し立てるケース。近年、このケースが非常に増えています。
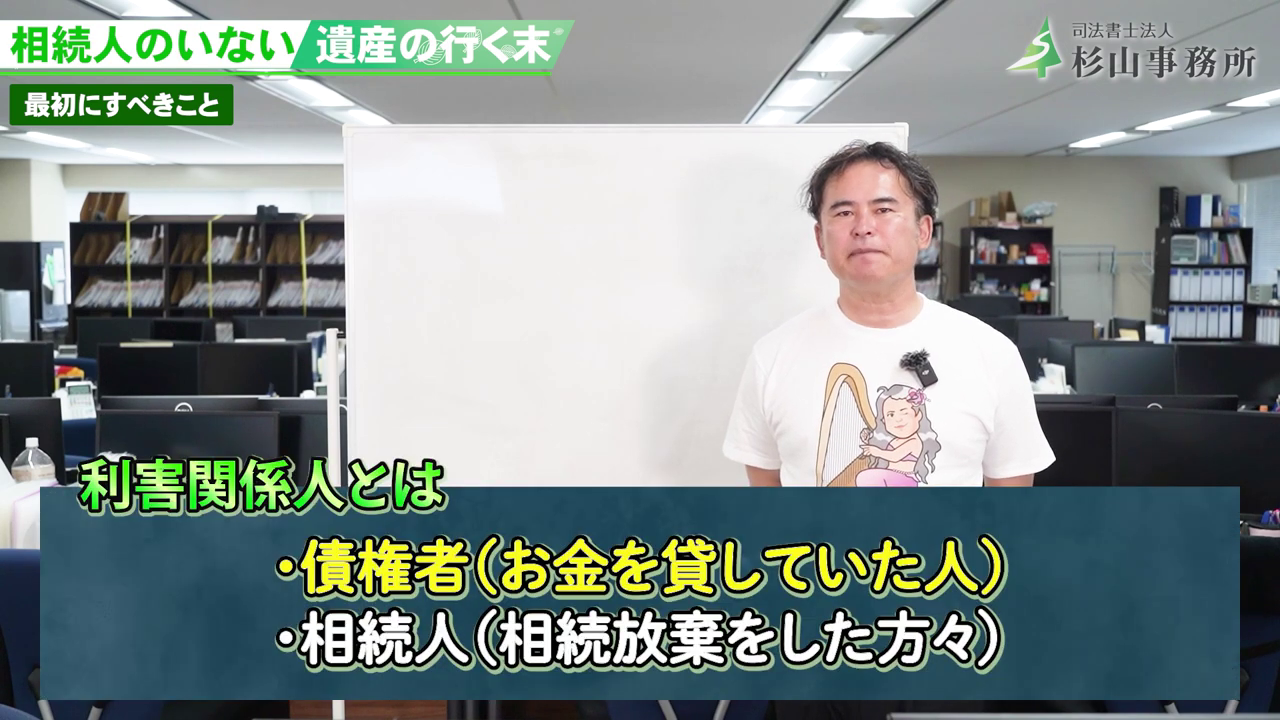
「相続放棄するなら、相続財産管理人の選任までセットで考える」。これが、不動産などの遺産がある場合の鉄則です。
【費用まとめ】相続財産管理人を選任するにはいくらかかる?
注意点として、この手続きには費用がかかり、その費用は原則として申立てをした人が負担します。
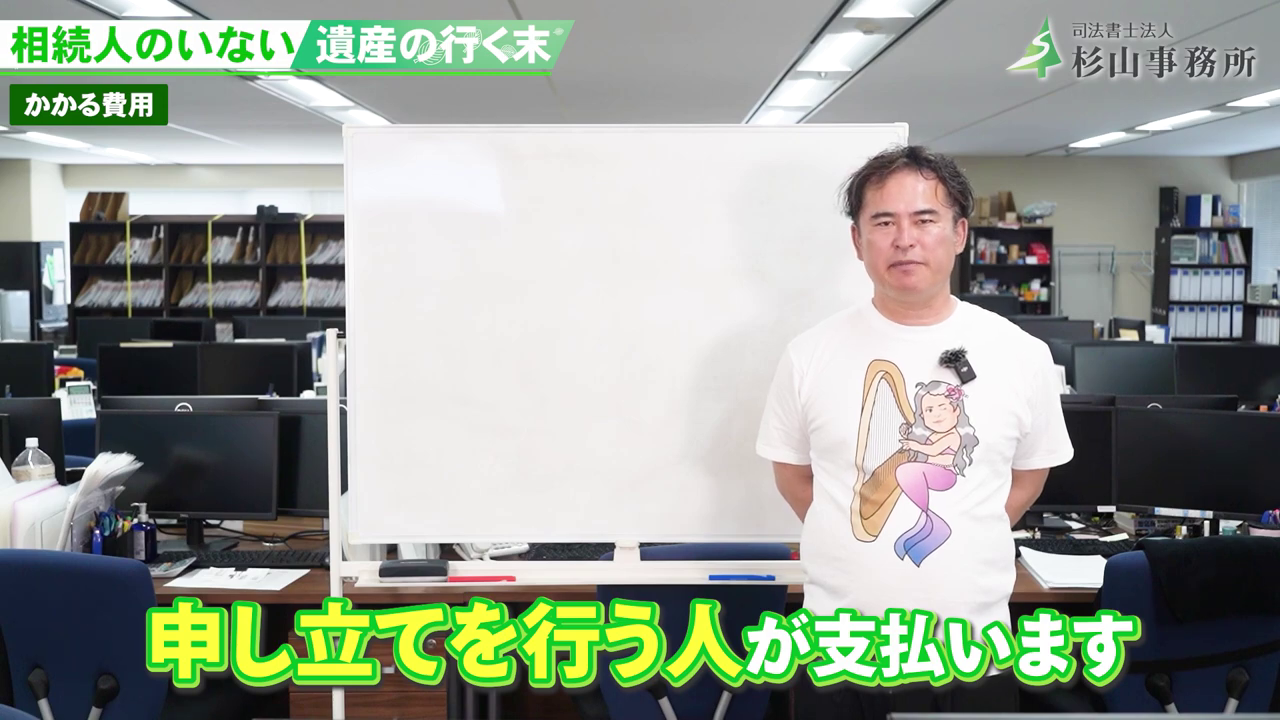
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
| 収入印紙 | 800円 | 申立書に貼付します。 |
| 郵便切手 | 数千円程度 | 裁判所からの連絡用です。 |
| 官報公告料 | 4,230円 | 国の広報誌に掲載する費用です。 |
| 予納金(よのうきん) | 20万円~100万円 | 管理人の報酬や経費に充てるためのお金。遺産の内容により変動します。 |
| 専門家報酬 | 依頼内容による | 申立てを司法書士や弁護士に依頼する場合の費用です。 |
最も大きな負担となるのが「予納金」です。これは、管理人が活動するための費用を前払いするもので、遺産が少なく経費をまかなえない場合に必要となります。高額になるケースも多いため、安易に申し立てられるものではないことを知っておきましょう。
国庫に納められるまでの流れ
相続財産管理人が選任されてから、遺産が国庫に納められるまでには、以下のステップを踏む必要があり、全体で1年強はかかると考えてください。
- 債権者・受遺者の確認(約2ヶ月)
管理人は「故人にお金を貸していた人はいませんか?」と官報で公告します。
- 相続人の捜索(約6ヶ月以上)
戸籍を徹底的に調査し、それでも相続人が見つからないか最終確認するための公告を行います。 - 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)の確認(約3ヶ月)
相続人がいないことが確定した後、「故人と生計を同じくしていた人や、療養看護に尽くした人はいませんか?」と探し、財産を受け取る権利があるか審査します。
※特別縁故者とは: 内縁の妻や事実上の養子など、法的な相続人ではないものの、故人と密接な関係にあった人のことです。 - 財産の清算と分配
管理人は不動産などを売却して現金化し、債権者や特別縁故者に分配します。 - 国庫への帰属
ここまでの手続きをすべて終え、それでも残った財産が、ようやく国のものになります。
まとめ:相続放棄はゴールじゃない!その後の責任も理解しよう
今回は、相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合の遺産の行方、そして相続放棄をしても残る可能性のある「遺産管理責任」について解説しました。
【本日の大切なポイント】
・相続放棄≠責任からの完全解放: 相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまで、または相続財産管理人が選任されるまで、遺産の管理義務が残ることがあります。
・相続人がいない遺産の行方: 最終的には国庫に帰属しますが、それまでには相続財産管理人の選任など、複雑な手続きが必要です。
・相続財産管理人選任の費用: 申立人が負担し、高額な予納金が必要になることも。
・放置不動産のリスク: 相続放棄後も管理責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
「相続放棄をすれば終わり」という単純な話ではないことが、お分かりいただけたでしょうか。
もし相続に関して少しでも不安な点があれば、ご自身で判断せず、ぜひ杉山事務所のような専門家にご相談ください。あなたの状況を正確に把握し、最適な解決策をご提案します。