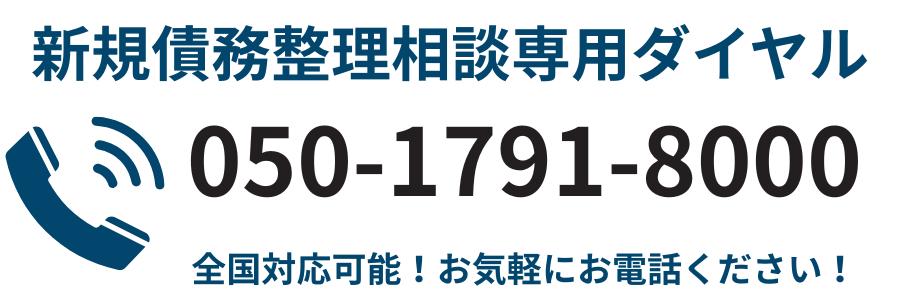「亡くなった親に借金があったみたいだけど、自分が払わなければいけないの?」
「相続放棄をしたいけど、何をしてはいけないのか分からない…」
大切なご家族が亡くなられた後、このような不安を抱えていませんか?
実は、相続放棄には厳格なルールがあり、知らずに取った行動が原因で、借金も含めたすべての遺産を相続せざるを得なくなるケースが後を絶ちません。
この記事では、司法書士法人杉山事務所の杉山先生の解説に基づき、相続放棄を考えている方が絶対に知っておくべき「やってはいけないNG行動」と、確実に相続放棄を成功させるためのポイントを、誰にでも分かりやすく解説します。
そもそも「相続放棄」とは?
【相続放棄とは】 亡くなった方の財産や借金を一切引き継がない手続きのことです。
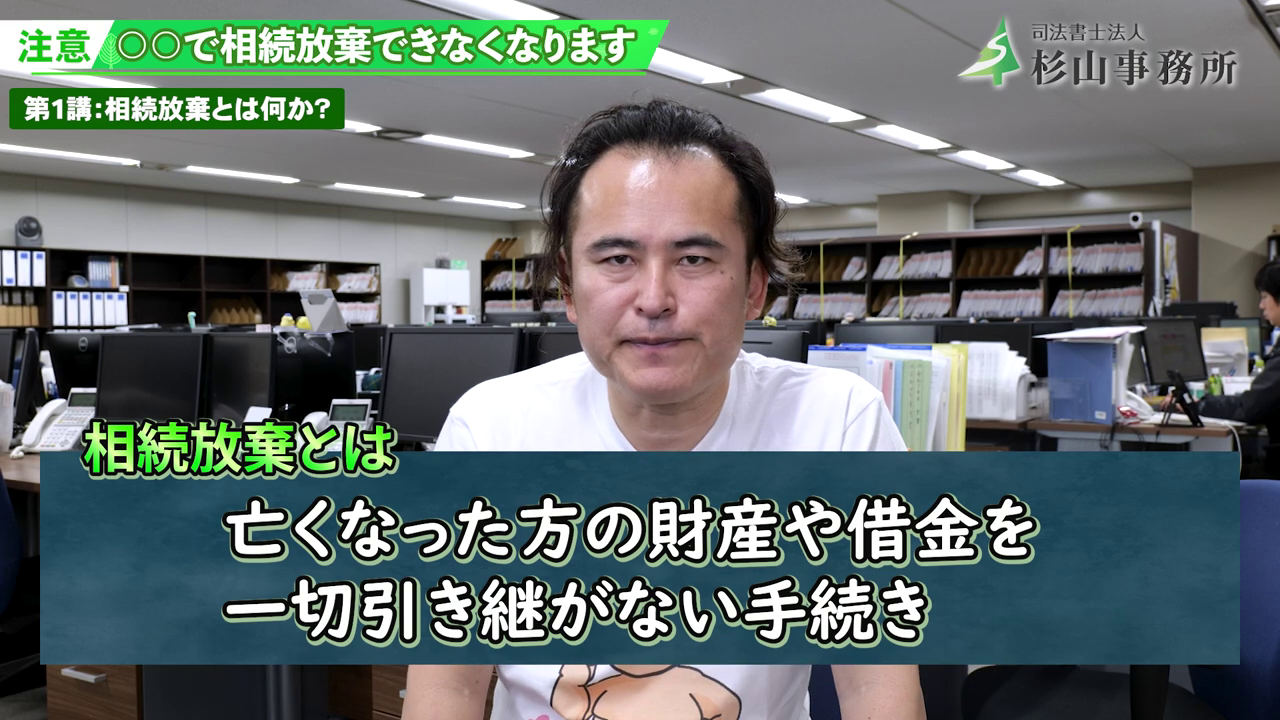
これを行うことで、借金を背負うリスクを回避することができます。
【相続放棄が選ばれる主なケース】
・被相続人(亡くなった人)に多額の借金がある場合
・遠い親族の相続が発生し、関わりたくない場合
・兄弟や親戚とトラブルを避けたい場合
しかし、相続放棄にはルールがあり、知らずにやってしまうと放棄できなくなる行動がいくつかあります。
【要注意】これをやると相続放棄できなくなるNG行動4選
「相続する意思がある」とみなされる特定の行動を取ってしまうと、法律上「単純承認」したことになり、後から相続放棄ができなくなります。
特に注意すべき4つのNG行動を、具体的な例とともに解説します。
NG行動①:相続財産を使ってしまう
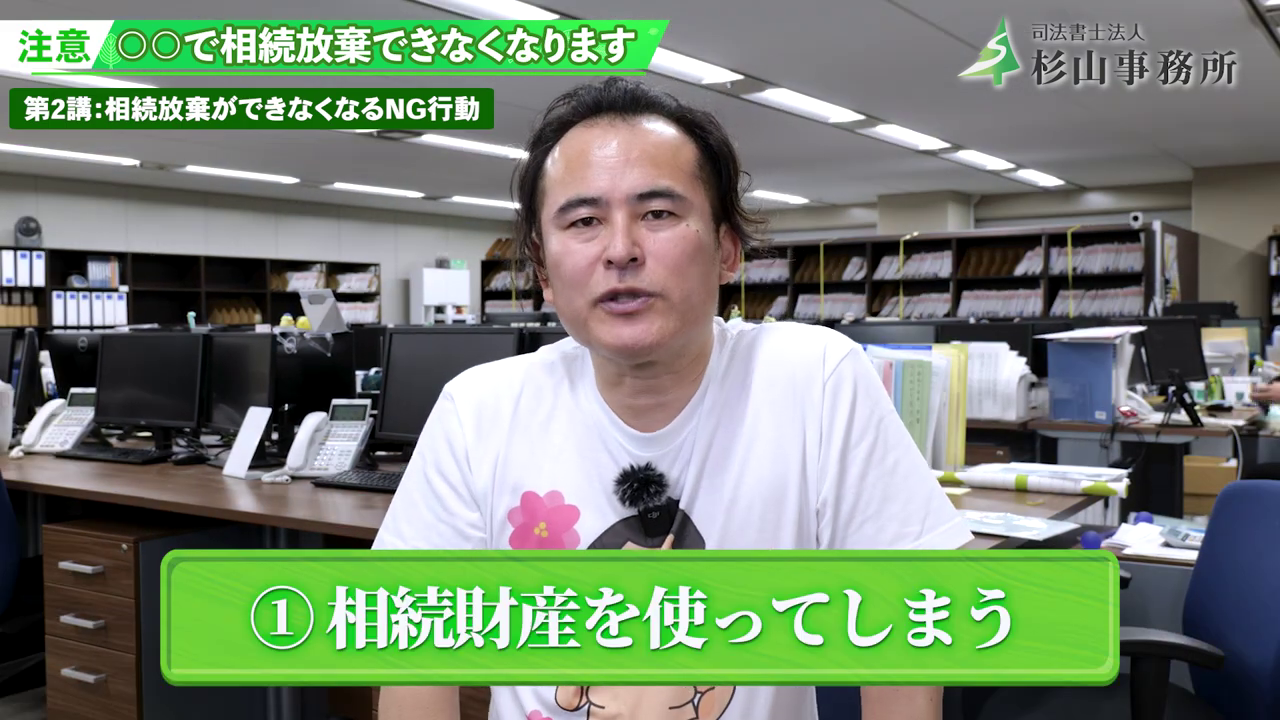
亡くなった方の財産を自分のために使うと、「遺産を相続する意思がある」と判断されます。
- NG例:
- 亡くなった方の銀行口座からお金を引き出し、自分の生活費や支払いに充てる。
- 亡くなった方の不動産や車を売却し、お金を受け取る。
- 亡くなった方が受け取るはずだった保険金や年金などを自分のものにする。
【ポイント】
葬儀費用など、社会通念上妥当な範囲での支払いであれば認められる場合もありますが、判断が非常に難しいため、遺産には一切手をつけないのが鉄則です。
NG行動②:被相続人の借金を一部返済する
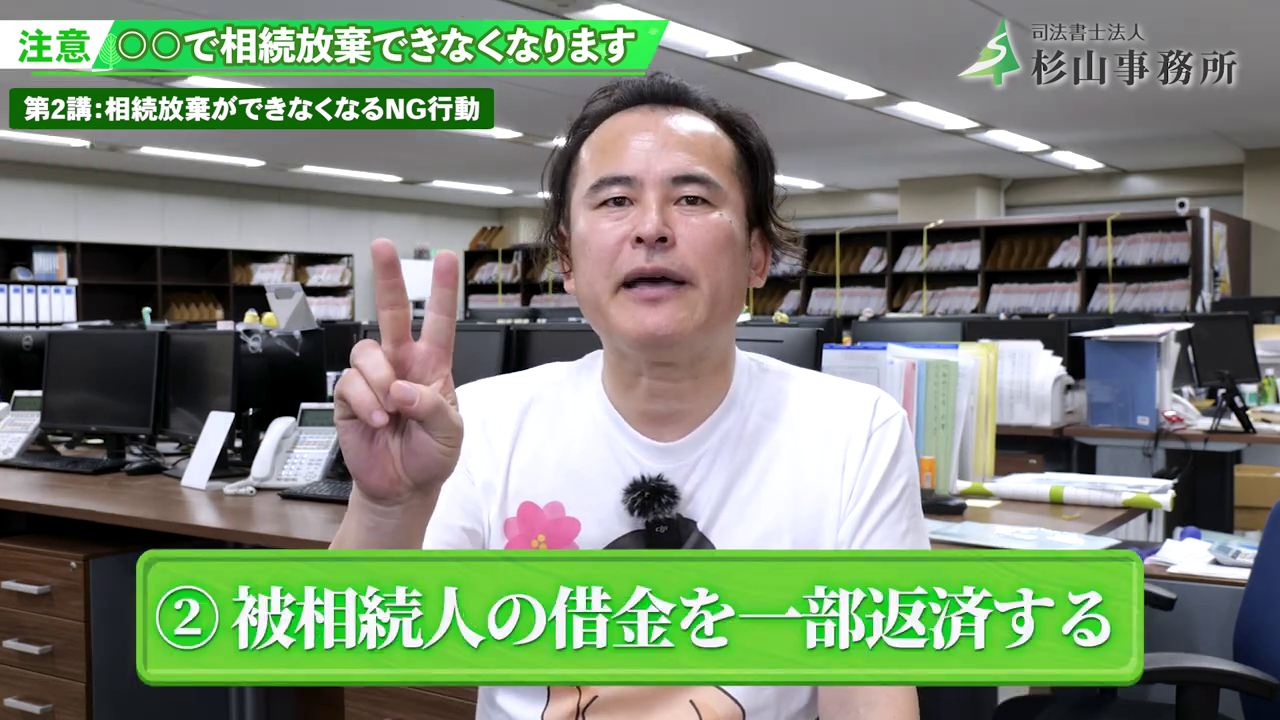
「少しでも返しておこう」という善意が、裏目に出ることがあります。
亡くなった方の借金を、相続人自身の財産から一部でも返済してしまうと、債務を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
NG行動③:遺品整理で価値のあるものを処分・売却する
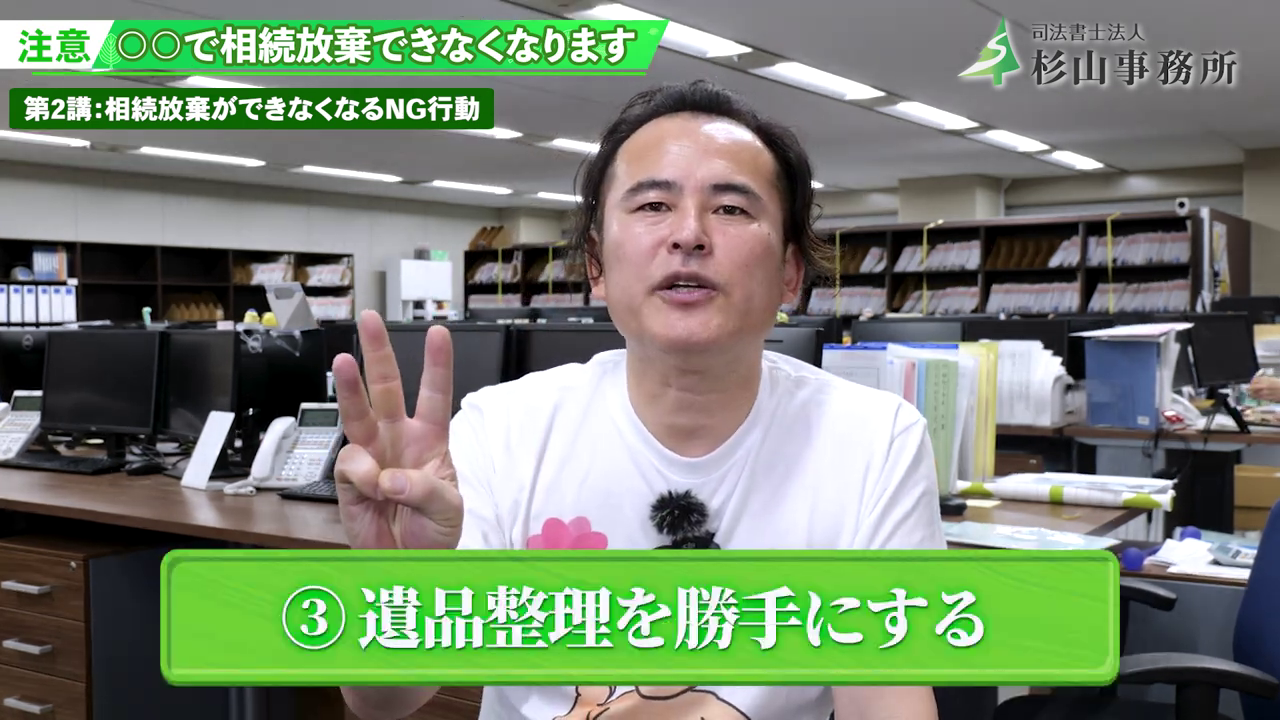
遺品整理も慎重に行う必要があります。形見分けのつもりでも、財産的価値のあるものを持ち帰ったり、売却したりするとNGです。
- NG例:
- 高価な貴金属、骨董品、ブランド品などを売却・処分する。
- まだ価値のある家具や家電をリサイクルショップに売る。
【ポイント】
価値があるかどうかの判断は素人には困難です。遺品整理は、相続放棄の手続きが完了するまで待つのが最も安全です。
NG行動④:相続人としての手続きを行ってしまう
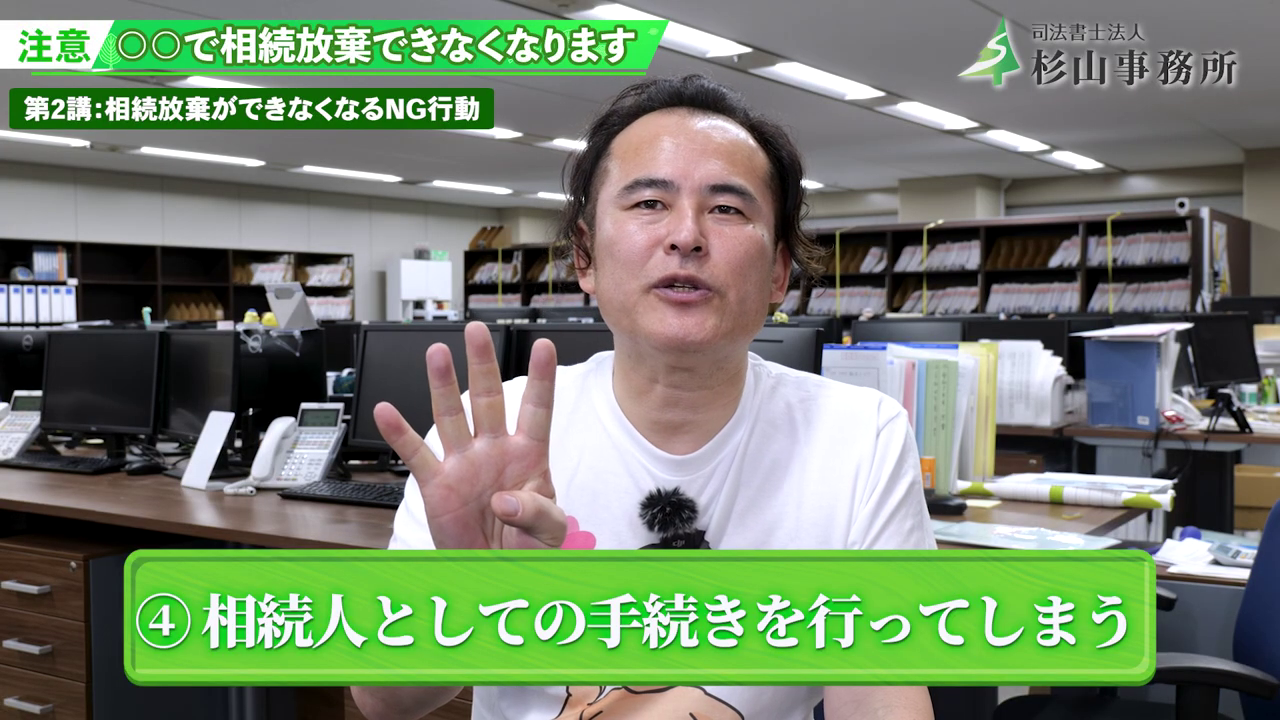
自分を「相続人」として公的な手続きを進めてしまうと、相続放棄ができなくなります。
- NG例:
- 遺産分割協議に参加し、合意書に署名・捺印する。
- 不動産の名義を自分に変更する(相続登記)。
相続放棄を確実に成功させるための3つの鉄則
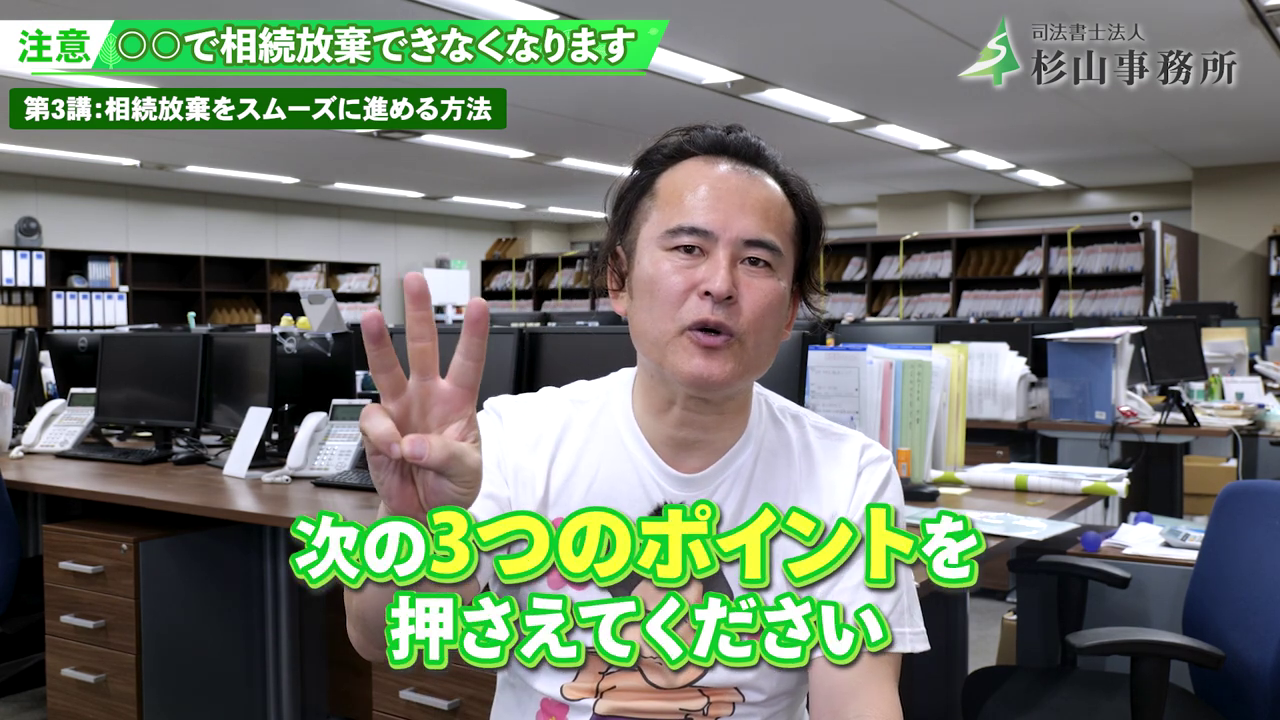
では、どうすれば安全に相続放棄を進められるのでしょうか?守るべき鉄則は3つです。
鉄則①:【3ヶ月が期限】早めに家庭裁判所に申し立てる
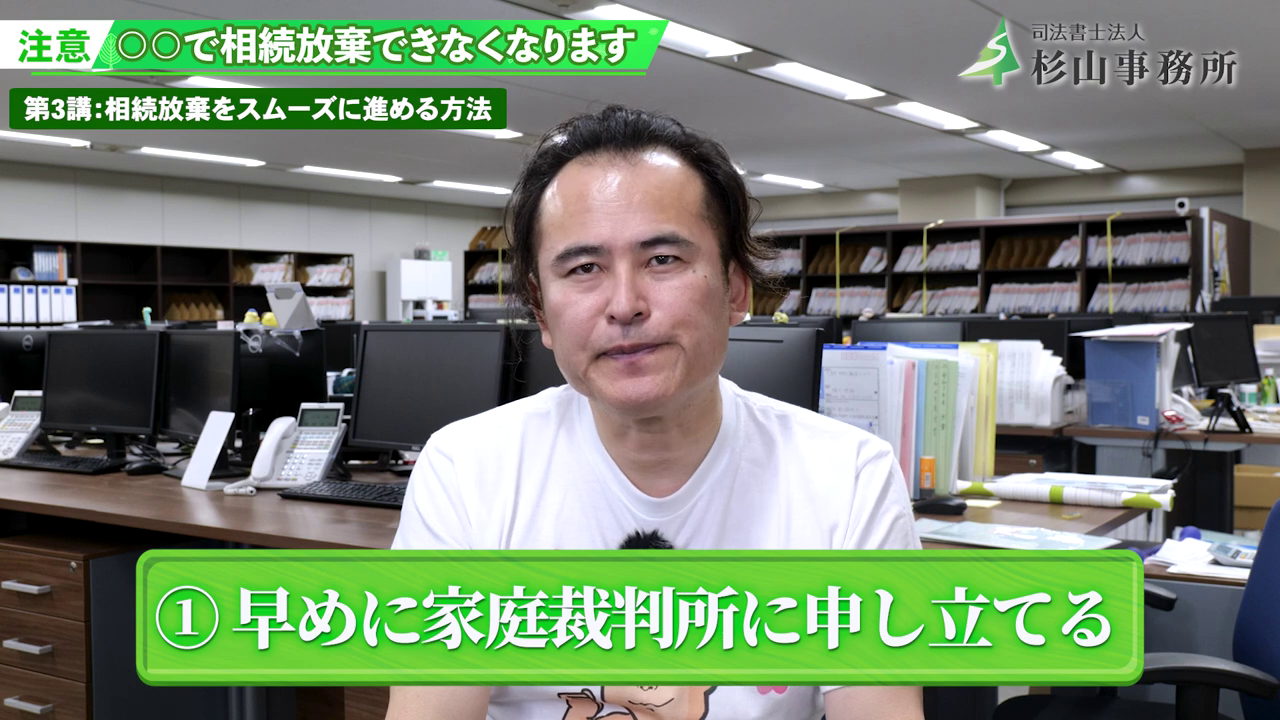
相続放棄には期限があるので、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に申立てが必要です。この期間はあっという間に過ぎてしまうため、迅速な行動が不可欠です。
もし3ヶ月以内に決められない場合は、裁判所に延長の申請をすることも可能です。
鉄則②:とにかく「何もしない」ことが重要
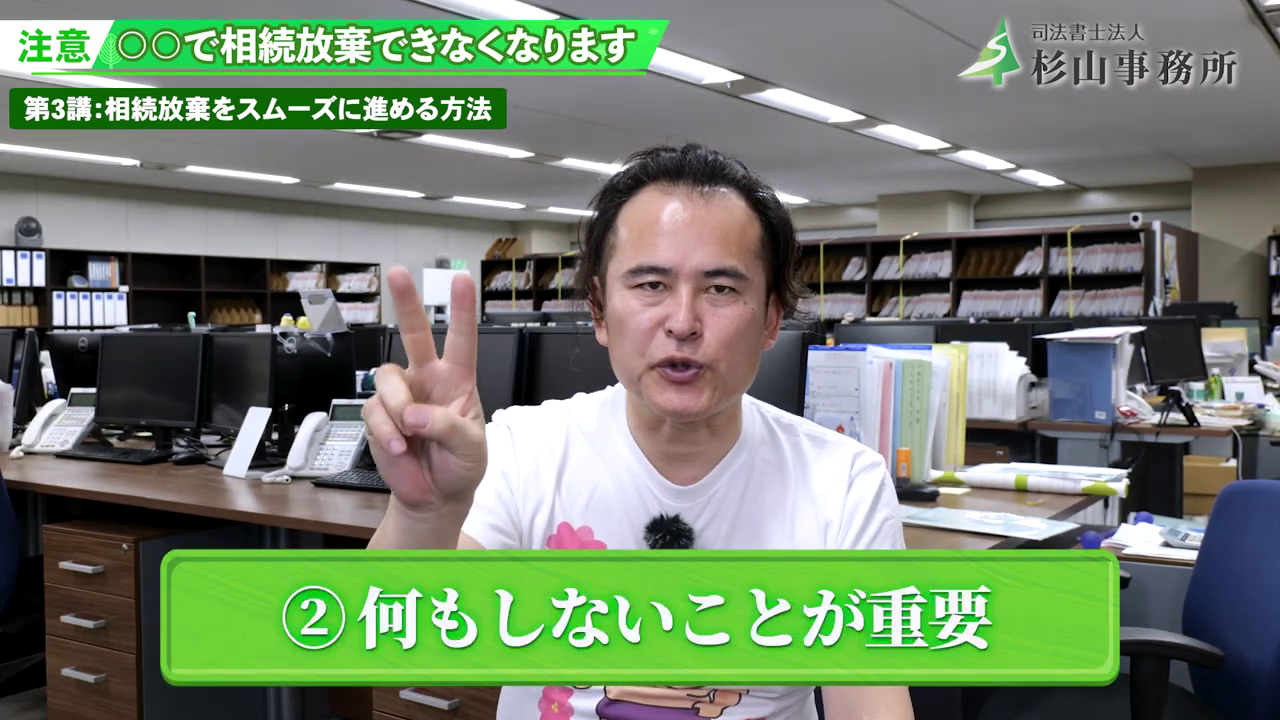
相続放棄の手続きが完了するまでは、亡くなった方の遺産には一切手をつけないこと。
これが最も重要な鉄則です。預金にも、不動産にも、遺品にも触らず、まずは手続きに専念しましょう。
鉄則③:迷ったらすぐに専門家に相談する
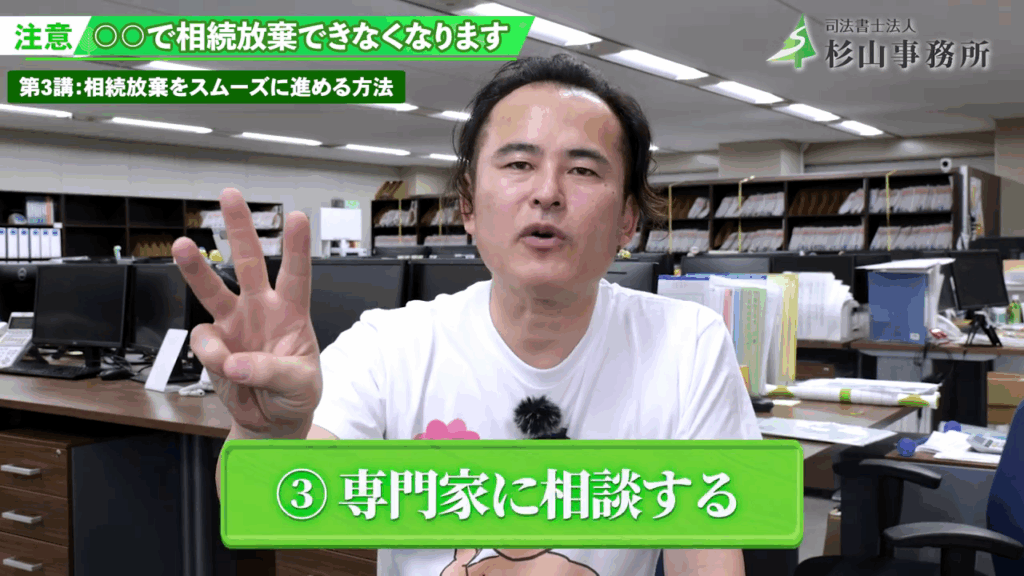
相続放棄は、一度失敗すると取り消しができません。少しでも不安な点があれば、自分だけで判断せず、司法書士や弁護士といった専門家に相談しましょう。専門家であれば、複雑な手続きを正確かつスムーズに進めてくれます。
実際に相続放棄をする際の注意点
それでは最後に、実際に相続放棄を行う際の具体的な流れと注意点を解説します。
結論から言うと、まずは家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うことが最優先です。
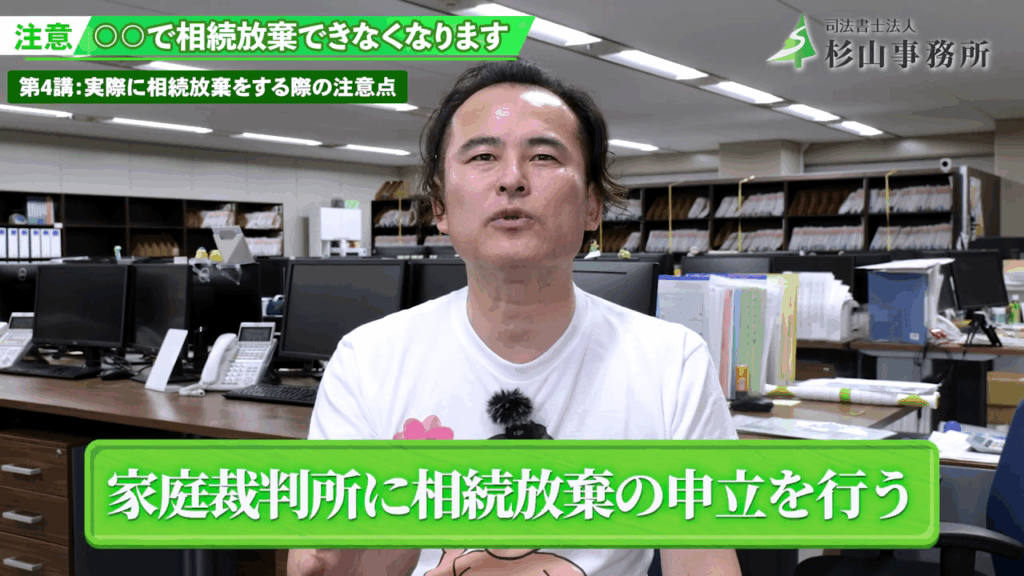
相続放棄の申込み3ステップ
ステップ1:必要書類を集める
まず、以下の書類を準備します。
- 相続放棄の申述書(裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)
- 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 申立てをする人(相続人)の戸籍謄本
※相続関係によっては、これ以外の戸籍謄本も必要になる場合があります。
ステップ2:家庭裁判所へ提出
書類が揃ったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。窓口への持参だけでなく、郵送でも申立てが可能です。
ステップ3:「受理通知書」を受け取れば完了!
書類提出後、裁判所が内容を審査します。
問題がなければ、相続放棄が認められた証として「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
まとめ:うっかりミスを防いで、確実に相続放棄を
本日は、相続放棄ができなくなるNG行動から、実際の手続きの流れまで解説しました。最後に、今日のポイントをもう一度おさらいしましょう。
1.財産を使わない:故人の預金引き出しや資産売却は絶対にNG。
2.借金を返済しない:善意の返済が命取りになります。
3.遺品整理をしない:価値のあるものの処分は手続きが終わるまで待つ。
4.名義変更などの手続きをしない:相続人としての行動は避ける。
この4つのルールを守り、「3ヶ月以内に専門家に相談して家庭裁判所に申し立てる」ことで、確実に相続放棄を進めることができます。
相続問題は、精神的にも時間的にも大きな負担となります。決して一人で抱え込まず、正しい知識を身につけ、私たち専門家の力を借りて賢く乗り越えていきましょう。
本日もご視聴、ありがとうございました。